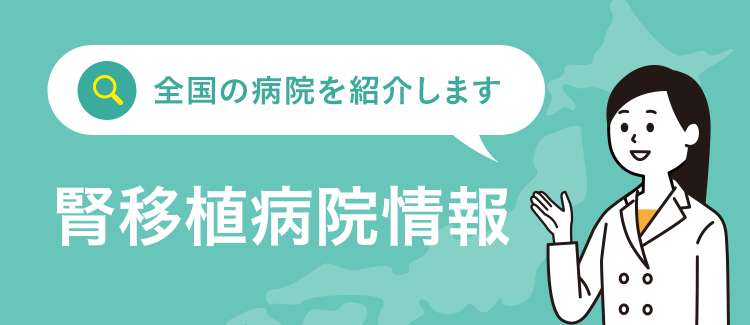2011年7月、北海道大学大学院医学研究科 腎泌尿器外科学分野(代表世話人:野々村克也)の主催で開催された「腎移植・血管外科研究会」の講演を、引き続き同大学院 森田研先生に解説いただきます。
今回は最終稿、「移植腎病理のアップデート」を解説していただきます。
6月25日(土)シンポジウム(2)
移植腎病理のアップデート 司会:深澤雄一郎先生、小川弥生先生
腎移植後の腎臓の病理検査は腎生検によって行われ、拒絶反応や薬剤の毒性、感染症などを正しく判断して治療するためには欠かせない検査です。世界的に移植腎病理所見記載を統一する会議が定期的に行われ、開催地名を取ってBanff分類と呼ばれています。
その中で現在最も論議を呼んでいる領域について、市立札幌病院の深澤雄一郎先生と、北海道腎病理センターの小川弥生先生に司会を頂き、3名の専門家から講演を頂きました。
まず最初に、名古屋第二赤十字病院の武田朝美先生から慢性抗体関連型拒絶の診断と問題点について概説を頂きました。ドナーから提供された腎臓組織に対する抗体が、移植したあとに慢性的にレシピエント体内で作られ続けると、抗体と腎臓との反応によって腎機能が低下していきます。
今まで「慢性拒絶反応」と呼ばれていて、なかなか治療法のなかった状態のうち、多くの場合がこの状態ではないかと言われています。実際にレシピエントの体内で作られている抗体を血液検査で測定したり、病理所見で抗体関連拒絶反応を診断したりして、分類を行い、どのような条件が揃えば慢性抗体関連拒絶反応と診断できるのかについて、詳細な報告を頂きました。
山口病理組織研究所の山口裕先生は、上記のBanff分類の策定に関わった経験から、この慢性的に移植腎に起こってくる病態の病理検査所見について、最近わかってきたことと今後の展望を実際の病理写真を用いて詳細に示されました。移植腎の尿を精製する部分である尿細管に、免疫細胞が侵入して炎症を起こしている所見や、腎臓組織の隙間に入り込む免疫細胞の数、尿を濾過するところである糸球体の「ふるい」の部分が構造的変化を慢性的にきたす所見が、この病理診断の要素となります。
腎臓の各部位に血液を運ぶ毛細血管の最深部である傍尿細管毛細血管内に、細胞膜の二重化や、血液凝固反応の一部の化合物の反応、免疫細胞の侵入があることが、特徴的な所見となり診断されます。この病理所見が腎臓の機能低下や蛋白尿の増加に繋がる可能性があります。
最後に、東京女子医大病院の清水朋一先生が、上記の慢性抗体関連拒絶反応に対する治療法について、実際に行った治療の内容と効果を報告されました。治療法は、抗体を作る働きを強く抑制すると言われている薬剤への変更、ステロイド大量療法、グスペリムス点滴治療、リンパ腫の治療薬であるリツキシマブの投与、大量ガンマグロブリン療法、血漿交換療法、脾臓摘出、抗T細胞グロブリンによる治療、などが適宜組み合わされて行われました。
現時点で、これらの治療法のどういった組み合わせが良いのか、については一定の見解が得られていないため、清水先生の示された結果は多くの施設の医師にとって参考になるものでした。免疫抑制剤を変更するのみでは、改善した方は居ませんでしたが、明らかな治療を行った場合の一部に、腎機能の改善が得られており、その割合は半数程度認められました。個々の治療法によって、身体への負担も変わり、個人差もあるため、有効と思われる治療法を数種類組み合わせて行うことが重要であります。
全体的な効果は、37人の患者さんに様々な治療を行って、移植腎機能が維持できた割合は76%で半数以上の方々の腎機能が治療前よりも改善または安定していました。合併症は少数でしたが、一部には感染症など重症になった方があり、要点としては、治療が必要な方の選定を正しく行うことと、今後治療法や薬剤の選択方法について、確立した方法を決めることであります。
解説:北海道大学大学院医学研究科 森田 研 先生