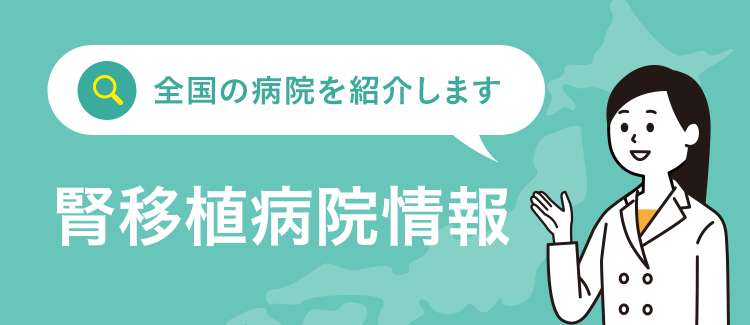2013年4月25日~28日に札幌市にて開催された、第101回日本泌尿器科学会総会での主な演題について、北海道大学 外科治療分野 腎泌尿器外科学 講師 森田研先生にご紹介・ご解説頂くシリーズの第3回目です。
2013年4月25日(木)から4日間、札幌市で行われました上記学会で腎移植に関係した講演を聴講致しました。各部門の専門家を招いて行われた企画講演(特別講演やシンポジウムなど)を今回ご紹介致します。毎度のことながら、内容についての解釈や文責は私にあります。事実と違う点がございましたらご容赦下さい。
ABO血液型不適合腎移植への挑戦、コペルニクス的発想の転換 (高橋公太先生 新潟大学 大学院医歯学総合研究科 腎泌尿器科病態学分野)
1901年にKarl Landsteinerが血液型を発見して以来、血液型不適合腎移植は行ってもうまく行かないと考えられてきました。一方、現在の日本では生体腎移植が腎移植件数全体の85%を占めていることから、血液型不適合移植が全体の25%を占めるに至っています。本来は献腎移植を増やすべきですが、献腎移植は待機期間が長いため、生体の適応拡大をやむをえず行っている状況です。最近25年の成果として生存率、生着率とも年々改善しており、2001年以降の成績はABO適合移植と遜色が無くなってきています。
ABO式組織/血液型関連抗原は、赤血球のみならず細胞表面、血管内皮にも発現しており、食物も含めて多彩なもの(例:かえで、もみじ)に発現があるため、自然と人間の血液中にそれに対する抗体が形成されることになります。欧米では、1967年の統計で血液型不適合の成績が悪いことが判明し、血液型の壁を越えての腎移植は行われなくなりました。地震の恐怖と同じように超急性拒絶反応の危険性がいつ起こるか判らないとされており、誰も挑戦する人が出現しませんでした。しかし、バスコ・ダ・ガマのインド航路の発見と同じように、この壁を越える努力がなされました。
1981年にSlapak医師が間違って血液型不適合移植を行い、急性抗体関連拒絶が起こったのですが、その治療の過程で血漿交換が有効であることを報告しました。その後、Alexandreが計画的に1982年から開始しましたが普及しませんでした。その後、高橋公太先生が血液型不適合腎移植を実際に日本で開始したところ、心配された超急性拒絶反応は最初の10数例で1回も起こらなかったので、その理由を調べるために、全国で行われている血液型不適合腎移植の統計を調べたそうです。すると、2日目までの期間に起こるとされていた超急性拒絶が実際は起こっておらず、1~2週間目までの急性抗体関連型拒絶が一部で起こっているに過ぎませんでした。移植後は臨界期間として2週間を過ぎれば安定することが判りました。免疫学的順応と呼ばれるこの状態(レシピエントに抗体は持続して存在するのに、抗体関連拒絶が起こらない、という矛盾)をどう説明するのかが高橋先生のライフワークとなりました。
やがて、基礎研究、臨床研究の結果、赤血球の表面にある抗原が問題なのではなく、血管内皮表面にある組織型抗原を問題にすべきであるということに帰結しました。ABO血液型抗原とABO組織型抗原の違いがあり、それは結合蛋白(アンカー蛋白)が異なるのであるということが新潟大学の田崎先生らの研究により明らかになりました。
また、実際に移植後1週間頃から起こって来る拒絶の原因となる抗体は、移植前からあるものが原因となるのではなく、移植後新たに産生される抗体であることが判明しました。移植することにより感作されて抗体が産生されるのを予防するためにBリンパ球をしっかり抑制しておくこと(数週間前からの脱感作療法、免疫抑制剤の使用、リツキシマブの投与など)が重要です。
抗血液型抗体が原因となっているように見える拒絶反応も、例えば拒絶反応の直前に感染が起こっていたりする場合は、感染による感作を受けており、病原体の表面にある糖鎖抗原に対する抗体が原因となり誘発されるため、移植後に感染症を起こさないようにすることも抗体関連拒絶反応の予防のために必要な点です。
今後の展開 : 血液型不適合移植は、心、肺、肝、などの移植にも応用可能です。また、腎移植後に急な輸血が必要になった場合に、AB型の血清を使用するべきである、などの、移植後の輸血対応のためのガイドラインが必要になることが考えられます。AB型凍結血漿の節約のためにも、抗体除去を行わない方法が模索されています。
輸血、血液型は、古い学問の領域に属しますが、思い込みや既存の常識では説明できないセレンディピティ(偶然の大発見)があり、興味深いと最後に述べておられました。固定観念を打破することが重要であるということです。
解説・文責:北海道大学 外科治療分野 腎泌尿器外科学 森田研先生