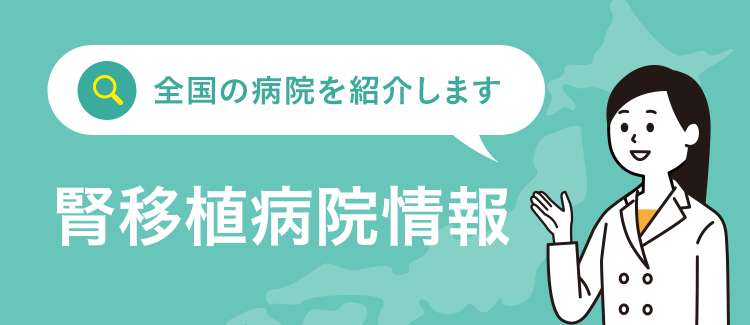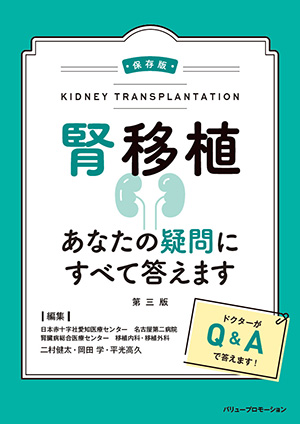2018年5月に2日間の日程で鹿児島市で行われた第34回腎移植・血管外科研究会にて、腎移植に関わるテーマで興味深い講演がございましたのでレポート致します。
研究会2日目「腎移植患者の希望に繋がる研究に光を」と題する教育セミナーが開催され、原田浩先生(市立札幌病院)と石田英樹先生(東京女子医科大学)の司会のもと、3名の日本の腎移植研究者がご講演されました。
研究は基礎医学に根ざした膨大な知識の理解が必要ですが、各講演者がわかりやすく噛み砕いて説明をしてくださいましたので、私が理解した内容をレポートいたします。厳密には正確ではない表現もあろうかと存じますがお許しください。
「腎移植者の希望に繋がる研究に光を」
座長:原田浩先生(市立札幌病院)、石田英樹先生(東京女子医科大学)
腎移植における免疫寛容誘導の最前線
堀田 記世彦先生(北海道大学)
腎移植成績は過去に比べて格段に改善しましたが、長期間の免疫抑制剤内服による合併症や慢性拒絶反応で、移植臓器が機能不全に陥ることがあるのが現状です。腎移植後10年間は無事に生着しても、10年以降に生着率が低下していくことが知られており、長期成績を向上させるためには、免疫抑制剤を中止しても移植腎が機能し続ける免疫寛容(レシピエントの免疫システムが拒絶反応を起こさなくなる)状態を作り出すことが必要です。そのためには、組織適合抗原の違いを認識するレシピエントの免疫機構を改変しなければなりません。人工的にレシピエントの血液の遺伝子を、ドナーの遺伝子を含む形(血液キメリズム)に修正する方法が、その具体策として以前から研究されてきました。
講演の最初に、北海道大学病院の1人のレシピエントの事例が示されました。そのレシピエントはEBウイルスという血液に感染する病原体が、移植後に初めて体内に入り、免疫抑制剤の投与で数年後にウイルスの感染によるリンパ組織の異常増殖が判明しました。10年以上が経過し、ウイルスの無制限な増殖を抑えるために免疫抑制剤を最小限まで減量しています。
服用している免疫抑制剤はエベロリムス1種類だけですが、腎機能は移植直後と全く変わらず安定しています。このような方々の血液キメリズムはどうなっているのか、ということが解明の鍵になります。
そこで、カニクイザルの腎移植の研究モデルを用いた免疫寛容実験を、人間の腎移植臨床に応用した米国での研究に、実際に参加された経験について紹介されました。
■カニクイザルの腎移植の研究モデル
腎移植前に全身放射線照射と胸腺放射線治療を行ない、ドナーのHLA抗原に反応するリンパ球を消去しておきます。腎移植後に一定期間Tリンパ球に対する抗体を投与して、ドナー組織に対する拒絶反応を抑制することにより、その後全く免疫抑制剤を使用することなく、13年もの間、移植腎が機能し続けているサルが研究室に居るそうです。
13年間、実験室の檻で飼育されているサルも可哀想ですが、重要な研究材料として種々の検査が行われ、予定手術である生体腎移植だけでなく、臨時手術となる献腎移植でも移植後に免疫寛容状態を誘導するための貴重な研究対象になっているそうです。
■人間への応用による免疫寛容
これらの実験結果を元にして、マサチューセッツ総合病院・スタンフォード大学・
ノースウエスタン大学では人間にこの技術を応用し、実際に移植患者さんの免疫寛容状態を達成しました。
3施設における方法には一長一短があります。その中でも完全にドナーの遺伝子をレシピエントに入れ替えてしまうことによる移植片対宿主反応※(拒絶反応の逆現象)を予防でき、組織適合性抗原が全く一致していなくても実用可能なマサチューセッツ総合病院の方法について示されました。
移植後にTリンパ球を一定期間抑制するために用いるベラタセプトという薬剤を日本でも使用することができれば、この臨床研究を日本においても行うことが可能だそうです。
※移植片対宿主反応(病):移植した臓器が宿主の細胞を攻撃して起こる免疫反応。
会場からは、最初に堀田先生が提示した症例における EBウイルスの移植後感染で、偶然免疫寛容になった状態で起こっている免疫学的メカニズムを詳しく解析することで、新たな方法を考えることはできないか、という質問がありました。
人間に臨床応用をするためには安全性の確保が必要で、実験的方法で腎移植後に生命に危険が生ずるようなことがあってはなりません。
解析することは可能であるものの、人工的にそのような状況を作り出すには、越えなければならない壁も多い、とのことでした。
異種移植研究の動向-過去・現在・未来-
田崎 正行先生(新潟大学)
■動物からヒトへの腎移植
臓器移植医療が進めば進むほど、必ず、生体・献腎移植のドナーが不足する問題が立ちはだかります。
移植臓器を供給するための方策として、人工臓器・再生医療・異種移植の方法があり、1900年代初頭にヨーロッパ各地で行われた動物からヒトへの腎移植実験が、再び脚光を浴びています。
人間とは違う動物からの移植は、細胞全ての膜にある糖鎖抗原がヒトと大きく異なることが原因で、激しい拒絶反応を起こすため、通常よりも強力な移植後免疫抑制療法が必要になります。
また、どの動物からヒトに移植するかについては、ホルモンや血液・薬剤などの特性上、人と大きな違いがなく使えるという条件や、その動物に特有の危険な感染症を有していないかどうか、臓器がニーズに合わせて大量に供給可能かどうか、ペット動物として人間と近い関係を持っていないか(倫理的側面)、といった基準で選択されます。その結果、ブタが全ての条件を満たしているそうです。
■ブタからサルへの腎臓移植
ブタからサルへの移植実験では、堀田先生の講演内容にもありました、胸腺やリンパ球に対する強力な治療を行なって移植前準備を行い、ドナーの胸腺を腎臓と一緒に移植したり、全身放射線治療や骨髄移植を併用したりすることが必要だそうです。この実験モデルでも血液キメリズムが数週間持続し、いったんは免疫学的に拒絶反応が抑えられましたが、レシピエントのサルが感染などの合併症で死んでしまうために生存率が下がるそうです。
そのままの状態のブタから臓器提供を行うのは障壁が高いため、ブタの遺伝子を改変してサルやヒトに近づけた人工的なブタを飼育したり、ヒトとは異なる糖鎖抗原の遺伝子をノックアウト(遺伝子が現れないように)するなどして、堀田先生の講演内容にも登場したベラタセプトを投与して移植を行ったサルが、現時点で異種移植での世界最長生着期間の記録を持っているそうです。この実験モデルでは、ネフローゼの原因になるポドサイトという腎臓の細胞に対してもベラタセプトが保護的に働いている様子が紹介されていました。
座長や会場から多くの質問が寄せられていました。こういった異種移植研究を臨床応用するにあたっても一定の制約があり、ブタの臓器をヒトに移植するという倫理的問題の他に、新たな薬剤を使用するにあたっての壁があるそうです。
血清N-glycanプロファイルによる早期抗体関連拒絶の予測
米山 徹先生(弘前大学)
血液型不適合腎移植の場合や、HLA不適合抗原に対する抗体が陽性となっている移植の場合に、レシピエントの体内に存在する抗体が原因となって起こる拒絶反応を予測するには、現時点では、血液中の抗体を測定したり、拒絶反応で機能低下した腎臓の生検病理組織検査で判断したりするしかありません。そこで、東日本の6つの移植施設から研究目的に集められた腎移植後の血液検査検体を調べ、血清中の糖鎖抗原の構造変化(N-glycan)を高感度で検出する方法を開発され、その結果を報告されました。
■抗体関連拒絶反応の予測バイオマーカーの探索
N-glycanという糖鎖抗原を36種類解析し、個々のレシピエント血清で、抗体関連拒絶反応の有無において何が異なるかを調べることにより、抗体関連拒絶反応を早期に検出するためのバイオマーカーにならないか調べました。
ある一定の計算方法でこの血清値のスコアを統計処理したところ、移植後3カ月以内に抗体関連拒絶反応を起こした場合は、移植後1日目にすでにこのスコアが一定以上の高い値を示していたそうです。実際にN-Glycan スコアが上昇する原因を調べたところ、免疫反応の一部として糖鎖抗原の変化をきたしていることがわかりました。一般的に抗体関連拒絶反応を起こす抗体は血液中のグロブリン分画と呼ばれる分子量の化合物中に存在するのですが、この糖鎖自体は別の部分に含まれている血液成分だったようで、今後の研究結果によっては新しい検査項目として臨床応用される可能性があるかもしれません。
■抗体関連拒絶反応の早期治療に向けて
抗体関連拒絶反応は急性・慢性に分かれて起こり、急性の場合は血漿交換や拒絶反応治療によって改善させることが可能ですが、慢性の場合は決定的に有効な治療法がいまだ不明で、治療困難です。この反応が移植後1日目という早期に判明するのなら、その後の拒絶反応の危険性に備えておくことが可能となり、薬剤投与量を増やすなどの有効な治療法を選択できることになります。
腎移植が臨床応用されてから、これまで50年以上の期間にわたり臨床研究が続けられてきており、腎移植成績は格段の進歩を遂げています。さらに高い理想に向かって、世界の最先端の研究が若手の日本人によって進められていることが実感できる教育セミナーでした。