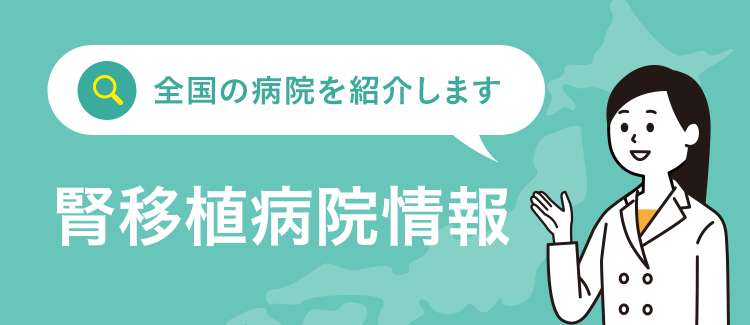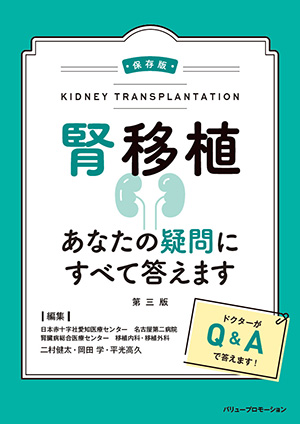平成27年2月4日から6日にかけて、名古屋にて開催されました臨床腎移植学会は、「賢腎移植への架け橋」というテーマで行われました。その本会前日に、東邦大学の相川厚先生と名古屋第二赤十字病院の後藤憲彦先生の司会で、内科医が腎移植において果たすべき役割について議論が行われました。講師は国内各地で活躍する4名の腎臓内科医と、イタリアから招請された先生でした。聴講した内容と学会プログラムを元にレポートします。
※レポートの1回目はこちらからご確認ください。
「長期生着を目指す上で、今、目を向けるべきこと -内科医の挑戦-」
移植後の腎疾患の再発について(九州大学 土本晃裕先生)
腎移植後に腎不全の原因となった腎疾患(原疾患)が再び発症することを再発腎炎と言いますが、一定の割合で原疾患が不明な場合があり、その場合は、再発腎炎なのか、移植腎に新たな腎炎が発症したのかが判別できないケースがあります。
土本先生は、まず、皮膚に特有な所見がある疾患において、皮膚生検により原疾患を診断できた例から、原疾患精査の重要性を示されました。その上で、再発腎炎の中で、移植腎機能が悪化する危険性の高い疾患群(巣状糸球体硬化症、IgA腎症、膜性増殖性糸球体腎炎、補体関連型膜性腎症など)は早期に診断することが重要であり、そのために必要な条件として、1日0.5g以上の蛋白尿を基準にチェックすることが望ましいとお話しされていました。また、定期的な腎生検で診断される、IgA沈着症や二次性巣状糸球体硬化所見は、その後の監視が重要とのことでした。
移植腎機能が悪化する危険性が高い疾患群の中でも、原因が明らかでない一次性(特発性)の巣状糸球体硬化症は、移植後再発で最も予後が悪い腎疾患で、1日3.5g以上の高度な蛋白尿(ネフローゼ症候群)が出ることが多く、ネフローゼ症候群で診断がついても腎生検では検出されにくいという特徴があります。治療法もまだ定まったものがなく、血漿交換、リツキシマブ投与、定期的なステロイドパルス療法などが試みられています。一方、原因の明らかな二次性(続発性)の巣状糸球体硬化症は肥満、薬剤性、妊娠、糖尿病、他の原因による糸球体数の減少などにより起こることがわかっていますので、何によって起こっているかを鑑別することが重要です。
膜性増殖性糸球体腎炎は分類上I型が治療抵抗性で、ステロイドパルス療法や血漿交換、リツキシマブ投与の他に、抗T細胞グロブリンという強力な拒絶反応治療薬を投与することもあるようですが、こちらはまだ効果が確定していません。
腎移植後の心血管系合併症について(名古屋第二赤十字病院 辻田誠先生)
腎移植の成績の向上に伴い、移植後長期間が経過した患者さんの長期生存を阻む第一の原因として、心血管系の合併症があげられます。
その中でも最も重要なものが、左心室の拡張、肥大で、それには貧血が密接に関係しているということでした。
貧血になると、酸素を運ぶために必要なヘモグロビン※1 濃度が下がるため、心臓がより多くの血液量を送り出す必要が出てきます。そのため、ポンプの働きをする左心室が肥大し、負担が増加します。心臓の筋肉を動かすエネルギーを作り出しているミトコンドリアが膨張し、高血圧、動脈硬化の悪化が認められます。従って、貧血を改善しないと心不全が悪化して生命予後に影響することになります。
しかしその一方で、国外のデータでは、ヘモグロビン濃度を高く設定しすぎると、血液が凝固しやすくなるため、血栓症による悪影響が出てくるようです。つまり、ヘモグロビン値は高すぎても低すぎても良くないということがわかっています。
日本人の適正なヘモグロビン濃度を調べるために、名古屋第二赤十字病院では目標ヘモグロビン値を10.5g/dl、または12.5g/dlに設定した二つのグループで心機能や腎機能を比較する臨床試験を行っていますが、まだ最終的な結論は出ていないそうです。この講演には会場から数多くのコメント、質問がありました。
慶応大学の中川健先生からは、ヘモグロビンを低下させる他の要因として、降圧剤であるアンギオテンシン系阻害剤や免疫抑制剤のミコフェノール酸モフェチルによる影響があるので、それらの薬の中止によるメリット、デメリットについて質問がありました。回答としては、個々の場合に応じた対策が求められるということでした。
神戸大学の西慎一先生からは、腎移植後の貧血を含めて、慢性腎不全全体における腎性貧血ガイドラインが現在改訂中であり、腎機能により影響を受ける鉄飽和度※2 の数値よりも、貯蔵鉄の指標であるフェリチン※3 値を重視した新たなガイドラインが近日発表されるとのことでした。
移植後の腎性貧血の検討を行っている新潟大学の斎藤和英先生より、日本人の適正ヘモグロビン値は、最終的には欧米よりも低めの12.5g/dl付近になるのではないかとのコメントがありました。司会の相川先生からも日本人の人種的な特殊性が指摘され、欧米で報告されているような造血ホルモン治療に伴う血栓症の合併症は殆ど起こらないのではないかということでした。この分野は、我が国独自の臨床研究を行う必要性がありそうです。
※1 ヘモグロビン
赤血球中の大部分を占めている血色素。赤血球中のヘモグロビンは、酸素を体内の組織に運び、代わりに二酸化炭素を受け取って肺まで運んできて放出し、再び酸素と結びついて各組織に運ぶという重要な役割を担っている。
※2 鉄飽和度
鉄飽和度(%)=血清鉄/総鉄結合能(TIBC)×100
血清鉄とは、血液が凝固して上澄みにできる淡黄色の液体成分(血清)に含まれている鉄分のこと。鉄はトランスフェリンという蛋白質にくっついて運搬され、それが血清鉄として測定される。
血清中のトランスフェリンの全体の濃度は総鉄結合能(TIBC)で示され、TIBCと血清鉄の値から、血清中の鉄飽和度(%)が計算される。
※3 フェリチン
鉄の貯蔵および血清鉄濃度の維持を行う蛋白質。
招請参加 (イタリアのジェノバより Ernesto Paoletti先生)
Paoletti先生からは前述の腎臓内科の先生方の講演に対して質問が出されており、日本でのワークショップに非常に興味を持たれている印象でした。
心血管障害に影響する要因としては、免疫抑制剤として重要な薬剤である、カルシニュリン阻害剤の血管毒性があげられます。その血管毒性を最小限にするために、エベロリムスやステロイドが併用されますが、各薬剤の副作用としてみられる、脂質代謝異常(高脂血症)や、糖尿病の合併頻度についてのお話がありました。
心血管系合併症による突然死のリスクは、腎移植後は減少するものの、ゼロにはならないため、それを減らすためにはカルシニュリン阻害剤やステロイドの長期投与量を減らす工夫や、腎機能の改善、脂質代謝異常の改善が求められます。
糖尿病の影響に関しては、移植前に糖尿病だった場合の方が、移植後新たに糖尿病になった場合よりも心血管系合併症が起こりやすいようです。
移植腎機能と心臓肥大は負の相関関係を示し、腎機能が良い場合ほど心臓肥大は起こりにくくなります。また、微量アルブミン※尿の増加や肥満は心肥大に悪影響をもたらします。血圧を正常化させることや喫煙をやめることは心肥大を改善するというデータも示していました。
一方、一般的には心血管系に保護効果があると言われているアンギオテンシン系降圧剤の使用については、数年前にまとめられた2つの疫学研究(多数の集団を対象とした統計データを抽出して行う研究)で、移植後の生存率に逆の結果が出ており、それぞれHeinze、Opelzらの報告が2006年の同じ医学雑誌(JASN:米国腎臓学会)に掲載されているということでした。移植後の生存率に対する影響については、さらなる検討が必要で、解明されるにはもう少し時間がかかりそうです。
※アルブミン:血漿蛋白の約6割を占める蛋白質。
■最後に
このワークショップを聴講して、腎移植も、より高いレベルの健康を追求する医療に踏み込んできていることを実感しました。医学の発展と腎臓内科的な管理法の発達、薬剤の進歩などにより、以前では考えられないような困難な条件も克服することが可能になってきています。医療者だけでなく、治療を受ける側の努力目標も同時に達成しないと、より高いレベルの治療効果は得られないということも見えてきます。つまり、移植前からの細やかな準備、管理を生かすために、喫煙の中止や肥満対策、服薬の遵守といった患者側の努力も、長期生着には非常に重要な項目であるということです。
解説・文責:北海道大学 外科治療分野 腎泌尿器外科学 森田研先生